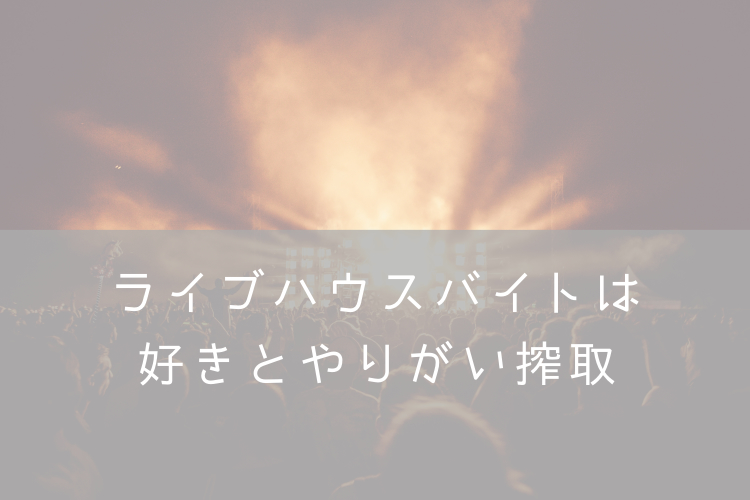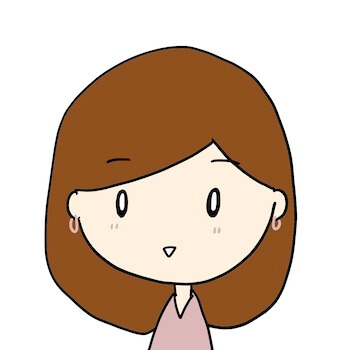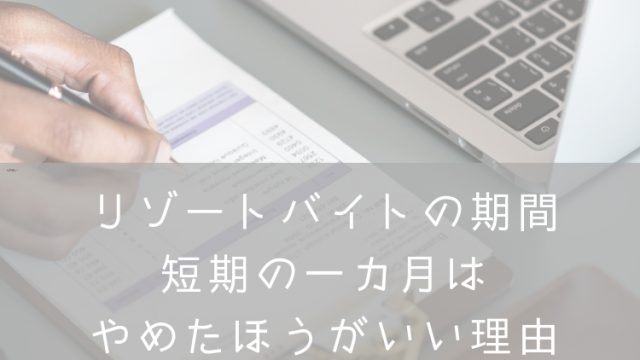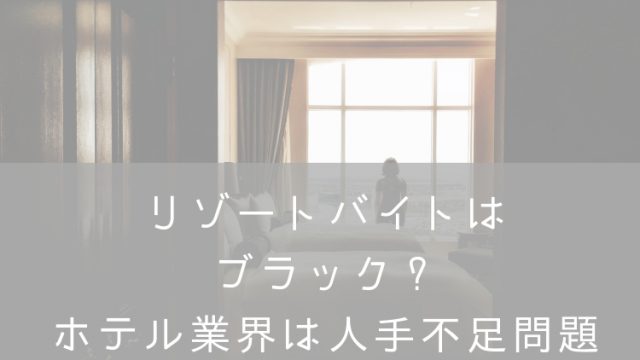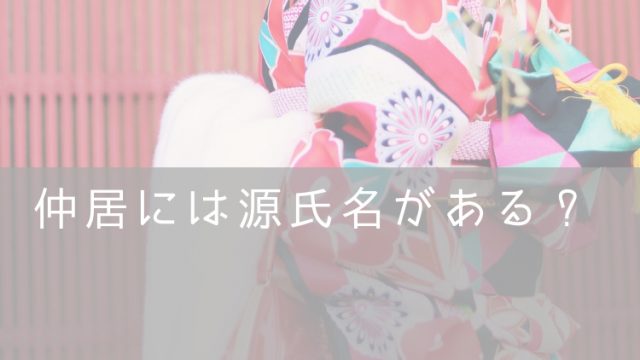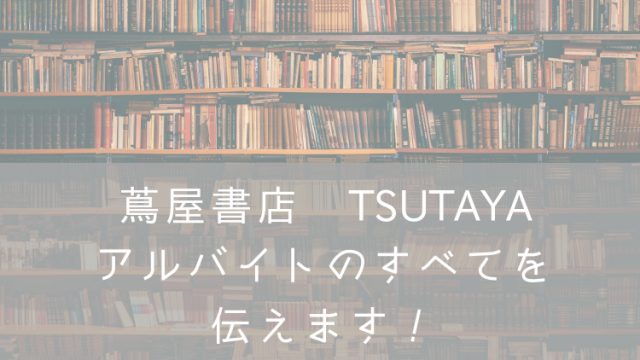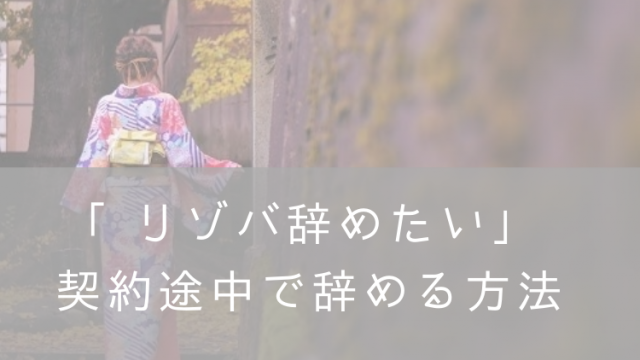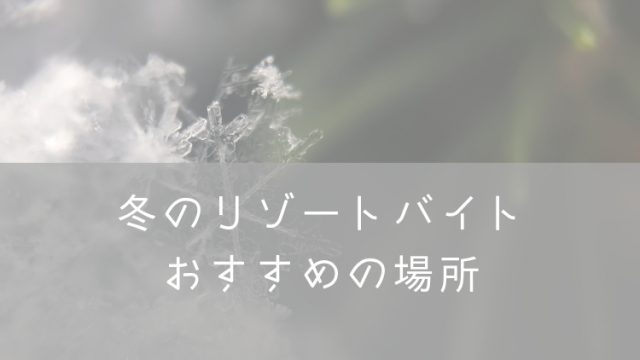- 音楽が好き!
- ライブが好き!
- フェスが好き!
という人は、たくさんいます。
これを見ているあなたも、きっと毎年大きなフェスに行くのではないでしょうか?
私も高校生のときにライブばかり行っていました。
好きなアーティストのライブに行って、間近で体感できる喜びは忘れられません。
そして、私は念願のライブハウスで働くことができました。
これから「ライブハウスで働きたい」と思っているあなたの参考になれば幸いです。
ライブハウスで働くためにしたこと

ライブハウスで働きたい!と思って行動していたわけではありません。
無意識に働きたいと思うようになって、気付けば働いていました。
これが役に立ったのかも?と思ったことを紹介します。
専門学校に入る
私は、音楽関連の専門学校へ入りました。
専門学校入学当時は、ライブハウスで働く予定ではありませんでした。
ただ、漠然と「音楽業界に行けたらいいなぁ」と軽く考えていました。
その業界の就職率も、業界研究もしていません。
「音楽が好き」という気持ちだけで、入学しました。
とにかく現場の経験を積む
ライブハウスやコンサートホールは限りがあります。
例えば、10人でやっているようなライブハウスで働きたいのであれば、その10人に入らなければいけません。
その10人という枠を自分で勝ち取るためには、どうしたらいいでしょうか。
未経験より経験者優遇の世界です。
まずは、専門学校の講師のコネで現場の手伝いに行かせてもらいました。
- 自分はどういう世界で働こうとしているのか
- こういう現場についていけるのだろうか
- そもそも音楽業界向いてるんだろうか
自問自答しながら、現場に行っていました。
考えてる余裕はなく、先輩に言われるがままに作業するのが精一杯です。
怒られたし、失敗もしました。
でも、終わったらなんか楽しかった。
無給でもいいから、自分のスキルを上げたかった。
今、思うと10代だから出来たことだと言えます。
とにかくライブに行く
月10回以上、ライブに行っていました。
ひどいと週3ライブです。
そんなによくお金あったなぁと思いますが、当時は掛け持ちで5つもバイトをしていたんです。笑
専門学校の先輩が、既にライブハウスで働いているというところもありました。
学生でも働くことができるんだなぁと感じ、ぼんやりと羨ましく思いました。
自分たちでイベントを開催
専門学校は「イベントプランナーコース」を専攻していたので、売れそうなインディーズバンドを発掘目的でライブハウスに足を運んでいました。
イベントを開催する目的で、ライブハウスに通うようになると、自然と人脈が広がります。
同じクラスの友人も積極的に活動していたので、その友人経由でイベントを自分たちで開催するようになりました。
実際にライブハウスを借り、バンドを呼んで、イベントを開催。
家族や友人にチケットを買ってもらったりしていました。
何回か開催しましたが、それはそれは色んなことがあり、私がライブハウスで働くようになり、その友人との共同開催は終わりました。
ライブハウスで働いたきっかけ
私は二箇所のライブハウスで働きました。
どちらのライブハウスも老舗です。
そして、どちらもコネで入りました。
一箇所目は、友人の紹介。二箇所目は、先輩の紹介。
同じ専門学校に通ってる友人と先輩でした。
入ってから知りましたが、音楽業界で働くというのは、とても難しいです。
ふつうに音楽関連の会社に就活する方もいますが、バイトから正社員になる人も多かったです。
そして、バンドをやっていた人ばかりで、楽器が弾ける人前提のような環境でした。
私自身アコギを買って練習しましたが、手が小さいので諦めました。(ピアノも)
メジャーなつまずき、Fコードで断念です。
しかし、楽器を弾けなくてもライブハウスで働くことができます。
私はコネで、どちらも紹介してもらって簡単な面接だけで入りました。
今ではアルバイト募集しているところも多く、最低賃金価格ではありますが時給も明示されています。
まずは「ここで働いてみたい!」というライブハウスに問い合わせてみてください。
実際にバイト募集って書かれてなくても、実は人手不足や辞めたがってる人もいます。
電話で聞いてみるのもありだと思いますよ!
ライブハウスで働くということ

チケットもぎり
一箇所目は、チケットもぎりのスタッフでした。
ライブハウス会場に入ると、ちらしを貰ってドリンク代を払いますよね。
チケットぴあや、ローソンチケットで購入するとチケットがちぎれるようになっています。
そのチケットをちぎるのが「もぎり」という仕事です。
あの入り口にいる受付スタッフですね。
主催会社やイベンターが入ってると、ライブハウス側のスタッフではなくイベンター側がやる場合もあります。
しかし、たいてい200~500人キャパのハコでは、ライブハウスでやることがほとんどです。
照明スタッフ
二箇所目は、照明スタッフとして入りました。
ここでは技術を身につけるまで半年間無給でした。もちろん、交通費も出ません。
学生で実家暮らしだからできたことですが、今でいうインターンシップのような形態です。
昔でいうと丁稚奉公です。
照明の技術を身につけないと、給料が貰えないということです。
最初は「タダでもいい!とにかくライブハウスで働いてみたい!」と思っていました。
無給なのにとても多くの時間を費やしたんです。
結果、私は半年後に給料が貰えるようになりました。
それがライブハウス業界の常識かはわかりません。
でも、そういうもんなんだって思ってしまうのです。
初めて入る世界で「こうなんだよ」と言われれば「そうなのかな」って思うのが、普通です。
それが普通と思ってしまった私。
そんな、ようやく照明スタッフとして給料がもらえるようになった私は、一体どのようなことをしてたのでしょうか。
ライブハウスの照明という職業

「照明すごい!どうやってやるの?」
とよく聞かれます。疑問だらけですよね。
照明の流れを書いてみました。
- 仕込み図を決める
- ステージを仕込む
- リハーサルをする
- シュートをする
- 本番のオペレーターをする
- バラシ
さっそく1の仕込み図から行きましょうか。
1:仕込み図を決める
ライブハウスの照明の場合は、ステージの仕込み図と呼ばれるものを照明スタッフが考えます。
仕込み図をもらっても、初めて行くライブハウスでは当日までどのように配置されているのかわかりません。
当日に変更することも、しばしばあります。
渋谷スターラウンジでは、照明基本仕込図がサイトに掲載されていました。
参考に見てみてください。ライト(灯体)の種類や当て方、色番号なども入っている仕込み図です。
[su_label type=”info”]参考[/su_label]渋谷スターラウンジ
ロスコとTBS(東京舞台照明) ポリカラーという会社のカラーフィルター(ゼラと呼ばれる)を使用しているところがほとんどです。
色番号は、その会社によって決まっていて、照明スタッフはそれを覚えています。
ワンマンライブの場合は、そのアーティストの世界にするためにイメージや曲を聴きこみ、仕込み図と色を決め、作り上げます。
また、バンドがいくつも出る対バンイベントなどは、どのバンドのイメージも作り上げられるような仕込み図に仕上げなければいけません。
いわゆる、無難な色が揃ってる感じです。(赤、青、オレンジ、黄色、水色、生(白)、ダークブルー)
私は、ポップなバンドを担当することも多く、淡くて可愛い色が好きでした。
このバンドのイメージカラーはこれ!と勝手に決めていたときもあります。
また、色に関しては次回語らせてください。笑
[su_label type=”info”]参考[/su_label]渋谷のライブハウスで8年ぶりに照明をした話
2:ステージを仕込む
仕込み図が決まると、ステージを作らなければいけません。
ワンマンライブだと、特に基本の仕込みからガラっと変えることもあります。
メンバーそれぞれの当てを作ったり、代表曲のためだけの仕込みを考えたりします。
ライブの前日、もしくは当日のバンドの入り時間前に仕込むことが多いですね。
色を変えるだけなら、すぐできますが、灯体(ライト)の位置を替えたりすると、とても時間がかかりました。
特に慣れてないと時間がかかるのが、この作業です。
どの延長コードを使えばきれいに配置できるか、電源の容量は大丈夫か、人間に近くないか(笑)など、様々なことを考えます。
ステージに立ったことがある人はわかると思いますが、照明はとても暑いです。
アーティストさんって、汗だくでしょう?笑
私は、仕込みの最中に脚立の一番上からステージに落ちたことあります。(無怪我)
それくらいハードな現場です。
仕込みのあと、照明卓で操作できるようにパッチという作業もあります。
3:リハーサルをする
仕込みが終わって、パッチという作業が終わると、照明卓で操作できます。
照明卓も音響のように、この色はこのフェーダーと言ったように割り振るんですね。
音響の仕込みをやっている時や、バンドがリハのセッティングをしている最中に、照明スタッフは、本番のオペレートをする色を照明卓に入れ込みます。
事前に音源を貰っている場合は、あらかじめ聴いて考えておくことができますが、リハでしかやらない曲は、リハ中に考えます。
もちろん、リハも全曲やるわけではありません。
一発本番の曲もありますが、これも合わせるんです。
すごいですよね。
これも経験で合わせることができますし、「次、落ちサビきそう」「サビ前にブレイクきそう」などわかるようになりました。
入れ込むのも時間が結構かかります。
バラードは簡単ですが、テンポの良い曲などは組み合わせたりするので、なかなか大変です。
4:シュートをする
ステージは、アーティストやスタッフが出入りするので、リハ中に灯体(ライト)の位置が変わってたり、ずれてることがあります。
それを最終確認のため、正しい位置に直すのです。
左右対称に、引きの画で見てもかっこいいように作り上げます。
本番中にズレてはまずいので、しっかり止めます。
5:本番
いよいよ本番です。
客電(客席の明かり)を消して、暗くなるときのお客さんの歓声は、ぞくっとします。
そして、スモークをばんばんたきます。
私は、スモーク好きだったので煙たいですが、きれいに照明が映えるのでスモーク使用のバンドは嬉しかったです。笑
そしてライブが始まります。
本番は、何回やっても緊張します。
自分の担当しているバンドでさえ、手が震えることも多かった。
それくらい毎回「良いライブになりますように」と照明をしていました。
私が働いていたライブハウスは、照明卓をさわるオペレーターと、ピンスポットを担当する二人で大体おこなっていました。
ピンスポットなしという指定のアーティストの場合は、オペレーターのみです。
ピンスポットの場合、バラードは自然にふわっと違和感のないように当てなければいけません。
これが難しく、きれいに当てれたときは「私天才かも」と心の中で叫びました。
6:バラシ
本番が終わると、バラシです。
基本の仕込み図もしくは、明日のライブ用の仕込み図にします。
この1~6まで、毎日毎日繰り返しです。
時間で言うと、大体13時すぎに入り、23時頃まで働いていました。
10時間以上働くのは当たり前で、休憩もリハ中に食べるくらいです。
休憩を1時間とるなんて、ありえない状況でした。
そして、週5という決まりもなく、人手不足や担当バンドのおかげで10連勤していたとかしょっちゅうでしたね。
最近では、いくつか照明の本が出てます。照明のことが気になる方は、より理解が深まります。
まだ照明を始めたばかり、照明のことをもっと知りたいという人は参考になるので読んでみてくださいね。
サービス残業という名の作業がたくさんある
お気づきかもしれませんが、仕込み図を考える時間、アーティストの曲の色を考えて決める時間が上記には存在していません。
これは、仕事中になかなかできることではなく、家で考えたりすることも多かったのです。
もちろん、その分の時給は出ません。
音源持ち帰って、通勤中や家で聴いてそのまま考えて、決めるんです。
この作業は結構楽しく、自分の想像通りのイメージが出来上がったり、かっこいいキメを思いつくと嬉しいんです。
しかし、それはお金が発生するものではありませんでした。
これこそ、やりがい搾取、ライブが好きだから、照明が好きだからという理由だけで、やってきた仕事量です。
ライブハウスの平均時給

やりがい搾取されていた私の働いていた時代は、時給は最低賃金以下でした。
もう10年以上前です。
今では違法ですし、監査が入り、時給が上がったそうです。
しかし、いくら10年以上前のこととは言え、600円台の時給ではなかなか暮らしていけませんでした。
時給600円スタートで、650円、700円、750円と上がってはいましたが、専門職種なのに本当に扱いが低いです。
平均でいうと、680円~900円台ではないかなぁと思います。もちろん、経験者や年数によって変わると思いますが、スタートは低いはずです。
ライブハウスではなく、コンサートスタッフは派遣会社を経由してる場合も多く、大量募集してるので、稼ぎたい音楽好きはコンサートスタッフをおすすめします。
ライブハウスで働くメリット・デメリット

そんな低い時給で、サービス残業も多く、労働時間も長い。
こんなライブハウスで働くメリットってあるんでしょうか。
しいて言えば、これがメリットなのかな?と思い出してみました。
メリット
- 好きなアーティストに会える
- ライブがタダで観れる
- チケット取ってもらえる
- 音楽業界に携われる
私も、高校時代に好きだったアーティストがライブハウスに来たときは、ちょっと感動しました。
喋れた!とは思いましたが、キャーキャーは言ったりしてません。w
別にサインも貰ってないし、握手もしてもらってないけど、ふつうに仕事として関われたことが嬉しかったです。
自分が休みの日でも、ライブを見に来ても良かったので、勉強のために観に行くことも多かったですね。
メジャーなアーティストは、やっぱり貫禄も違いますし、外オペと呼ばれる専用の照明スタッフを連れてることも多く、学ぶことも大きかったです。
自分の働いているライブハウスの他に、店長のコネや親会社のコネで、アリーナクラスの有名アーティストのチケットも取ってもらえました。
ファンクラブじゃないと、なかなか取れないアーティストも取ってもらっていたので、これは単純にラッキーでした。
そんな音楽業界にいると、自分のライブハウスだけでなくイベンターやチケット会社とも交流がありますし、他のライブハウスのスタッフとも関わるようになります。
顔も広くなるし、バンドの子にも覚えてもらえるし、中にはお客さんにまで顔バレしている状況でした。
お客さんに「照明よかった!」と言ってもらえることもあり、私がやってるって知ってるんだ…と思い、嬉しかったですがこわかったですね。
人脈を広げたい、今後も音楽業界で生きていきたい人にはライブハウスで経験を積むのもいいと思います。
デメリット
- 給料が低い
- 年齢を重ねると続けられない
- 出会いがバンドマンしかいない
時給が低いので、実家暮らしも多く通勤も大変でした。
もちろん、福利厚生も充実していないので有休なんてありませんし、交通費も貰えなかったです。
ただのブラックか。と思えばそれまでですが、これが通常運転でしたね。
また、私は25歳までに辞めたいと思っていて、宣言通りに辞めましたが、30、40になっても続ける気力も体力もありません。
長く続ける仕事というより、若いときにしかできない仕事だと感じました。
長く続けていきたい、正社員で働きたい人はイベント会社や音響(照明)会社の正社員の方が良いです。
これもなかなか見つけるのも転職も難しいですが、まずは探してみてください。
それでもライブハウスで働きたい人へ
やりたいならやればいい!
私は頑固でした。
ライブハウスで働く!と決めたら、親に反対されても給料が低くても「やりたいことはやる!」と思いながら生きてます。
自分がやりたいと思ったらやればいいです。
それより、もっとお金が欲しい!稼ぎたい!と思うなら、私はおすすめしません。
ライブハウスで働くことがライブの仕事だけではありません。
様々な人が関わっています。
- ブッキングマネージャー
- 音響
- 照明
- ドリンカー
- チケットもぎり・受付
ライブハウスでは、このような職種しかありませんが、音楽・ライブに関わる仕事は以下です。
- イベンター
- プロデューサー
- 舞台監督
- チケット制作
- ミュージシャン
- レコーディングディレクター
- スタジオミュージシャン
- レコード会社
- 音楽学校の講師
- 作詞家・作曲家・アレンジャー
まだまだあります。
興味がある仕事は、やってみたらいい。
勿論、20代から活動している人もいますが、30代で転職した人も多いです。
是非、自分がやってみたいこと、興味があることは一度やってみてほしいです!
アルバイトEXで探すのがおすすめな理由
私のイチオシは、アルバイト応募から採用されてお祝い金がもらえる「アルバイトEX」からの応募です。
自分の働きたいバイトができるのに、ちゃんと申請するだけでお祝い金がもらえます。
もちろん「お祝い金対象」な求人しかもらえません。しかし、いちばん先に求人を探す癖をつけておけば、見落とす必要なし!
全国の求人サイトの情報が凝縮された「アルバイトEX」でまずは求人を見てみましょう!
タウンワークでイベントスタッフから探すのもおすすめ
音楽の仕事に興味があるけど、ライブハウスは敷居が高いと思っていませんか?
私も実はそう思ってました。
ただ、どうしても音楽関連の仕事に就きたくて始めたのが「コンサートスタッフ」のバイトです。
チケットもぎりや、物販スタッフ、会場案内などを体験できて憧れのアーティストのライブも働きながら聴けちゃいました!
今では良い思い出!
短期から募集しているので、まずは求人を探してみてくださいね!
バイトルでイベントスタッフから探すのもおすすめ
公式サイトが見やすく探しやすいのが「バイトル」です。
気になる同僚の年齢層から男女比、職場の様子までわかってめっちゃ便利!
人気バイトはバロメーターで教えてくれるので、気になるバイトは早めに申し込むのがおすすめ。
まずは、「コンサートスタッフ」で検索してから選んでみましょう!